ユダヤ人の歴史【鶴見太郎】
ユダヤ人の歴史
| 書籍名 | ユダヤ人の歴史 |
|---|---|
| 著者名 | 鶴見太郎 |
| 出版社 | 中公新書(324p) |
| 発刊日 | 2025.01.25 |
| 希望小売価格 | 1,188円 |
| 書評日 | 2025.05.18 |
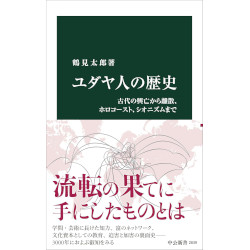
去年だったかテレビのニュースを見ていて、あれっ、と思ったことがあった。イスラエルがガザに侵攻し多くのパレスチナ人が犠牲になったことに抗議して集まった、ニューヨークの集会の映像。そこに集まった人々のなかに、黒服の上下に黒帽子をかぶった数人の若者がいた。
彼らはユダヤ教正統派(ハシド派)に属する人たち。ブルックリンにはかなりの数の正統派の人々が暮らしていて、僕もニューヨークに滞在していたときその一帯を訪れたことがある。街路を歩く男性はみな黒づくめ、そこだけ別世界のような光景だった。正統派に定められた格好とはいえ、イスラエルに抗議する集会に一目でユダヤ人とわかるそのような服装で参加するのは、かなりの決断と覚悟がいることだろう。いまトランプ大統領は「イスラエルに反対する者=反ユダヤ」という強引な構図で抗議する若者を取り締まったり大学に圧力をかけたりしているが、そうした思い込みや単純化から何が抜け落ちるのか、この一瞬のニュース映像からもわかる。
『ユダヤ人の歴史』は、ロシア・東欧ユダヤ史を専門とする著者が、古代から現代までのユダヤ史を通史としてまとめた一冊。ユダヤの歴史といえば、たいていの人は古代ユダヤ王国の滅亡やキリスト教・イスラム教との関係、そこから一気に現代に飛んでナチスによるホロコーストとイスラエルの建国、ぐらいしか思い浮かばない。小生もご多分にもれず、古代と現代の間に横たわる遥かな時間のユダヤについての知識はほぼ空白になっている。このところポール・オースター『4321』、アイザック・シンガー『モスカット一族』とユダヤ人作家による長編小説を読んだり(2冊とも本サイトで取り上げた)、ネットフリックスでニューヨークのユダヤ教正統派を素材にしたドラマとドキュメンタリーを見たこともあり、本書の新刊広告を見てすぐに書店に行った。無論、イスラエルのガザ侵攻という戦後の国際秩序を無視した強権的ふるまいの背後に、どんな歴史が横たわっているかを知りたかったこともある。
その通史のなかから興味深かったこと、知らなかったことをいくつか取り上げてみたい。
まずは古代。ユダヤ教が一神教としてどう成立したのか。といってもこの時代は歴史的史料が少ないので、主に旧約聖書の記述から読み取るしかない。よく知られた「バビロン捕囚」は、バビロニアによって滅ぼされた南ユダ王国(首都はエルサレム)の王と多数の住民がバビロニア王国に連れ去られ、そこで捕囚としての生活を余儀なくされたことを指す。とはいえバビロニアは旧ユダ王国の住民を比較的まとまった形で住まわせ、半自由民として農業も営めたので、ある程度の一体感を保つことができた。
国家を失ったユダヤ人がばらばらにならず、民族としてまとまり続けるための結節点となったのがユダヤ教だった。その核心はヤハウェと呼ばれる、世界を司るただ一つの神に対する信仰である。この時代、民族はそれぞれに違う神を信仰しており、戦争は神々の戦いであると考えられていた。でも、世界を司る神が一つなら、バビロニアを司る神もユダ王国を司る神も同じ神であり、ユダ王国の神がバビロニアの神に負けたことを意味しない。自分たちがこのような境遇にあるのは、神との契約に背いたために神の怒りを買ったからなのだ。
「ユダヤ教の場合、大きな国家や帝国に支配されるなかで、そこにおける神々と差異化し、自らのアイデンティティを保つ必要があったことで、次第に排他的一神教の傾向を強めていった」
バビロニアはその後、ペルシア帝国に滅ばされる。ペルシアは征服した異民族に比較的寛容だった。ユダヤ人が故郷カナンの地に戻ることを許したが、バビロニアで生活基盤を築いた大多数のユダヤ人はこの地に残った。「多くはペルシア帝国支配下で、唯一神信仰と立法の遵守によって民族の一体性の維持を図った」のだった。その後、ペルシアはアレクサンドロス大王に征服され、ユダヤ人はその文化圏へ、地中海沿岸各地へと散った。
ユダヤ教と、そこから枝分かれしたイスラム教、キリスト教との関係も興味深い。イスラエルというユダヤ国家とイスラム勢力が対立している現在から見ると意外だが、イスラム圏とユダヤ人の「相性はいい」そうだ。国家を持たないユダヤ人は家族や共同体単位でユダヤ教の律法に従って日常を送るが、それ以外のことでは暮らしている国の法に従順であることを戦略に生きのびてきた。中世に勢力を拡大したイスラム帝国では、ユダヤ人は税金を払えば「庇護民」として自治を認められている。なかでもイベリア半島のユダヤ人は大勢力となり、後にイスラム圏とキリスト教圏との文化的な橋渡し役を果たすことになる。
一方、キリスト教との関係は複雑だ。ローマ帝国がキリスト教を国教として以後、キリスト教圏ではユダヤ人を「生かさず殺さず」という、その時々で利用と迫害の両面を持った存在として対処してきた、と著者は言う。キリスト教会も世俗権力も、主に金融・商業に携わるユダヤ人に特権を与えて保護し、金づるとして利用した。しかしこの癒着は、庶民から見ればユダヤへの反感となる。それが爆発したのが十字軍遠征の過程で、「ユダヤ人がキリスト教徒の子供の血を食う」というデマが広がりユダヤ人襲撃が繰り返された。ユダヤ人は黄色いバッジをつけることを強制されたりもした。
「反ユダヤ主義は、反ユダヤ的なキリスト教徒とユダヤ人が対峙する単純な構図から生まれ、暴力に発展するのではない。ユダヤ人を金づるとして利用する権力者と、それを腐敗と捉える庶民のあいだにユダヤ人が挟まれるという三者関係こそが、一定期間秩序を維持しながらも庶民の反ユダヤ感情を蓄積していく。政変や不況などでこの権力者のタガが外れたとき、民衆の怨念は一気にユダヤ人に向かうことになった」
近世。「ディアスポラ(撒き散らされた者の意)はさらなるディアスポラを呼ぶ」。現代ユダヤ人の二大系統は「スファラディーム(スペイン系)」と「アシュケナジーム(ドイツ系)」と呼ばれる。イベリア半島がキリスト教徒によって再征服された後、ユダヤ人はスペインを追放された。彼らは主にオスマン帝国、ポルトガル、オランダへと逃れていった。なかでアムステルダムはオランダが大航海時代に発展するにつれスファラディームの商業の一大拠点となった。一方ドイツにも、早くからユダヤ人を追放したイギリスやフランスに比べ多数のユダヤ人が住んでいた。が、15世紀までにドイツからも追放され、ユダヤ人は主に東方へ逃れた。そのアシュケナジームを歓迎したのはポーランドやウクライナで、ユダヤ人は主として貴族から土地の管理や徴税を請け負った。しかし農民から見ればユダヤ人は、「農民の搾取者」という、ここでも負のイメージが広がっていった。
近代。近代にはポグロム(反ユダヤ暴動・虐殺)、ホロコーストという反ユダヤ主義の「世界史上最悪の悲劇」が生まれた。20世紀初頭、世界で最もユダヤ人が多く住んでいたのはロシア帝国(現在のポーランド東部、ウクライナを含む)だった。この地域のユダヤ人には貧困層が多く、大量の移民としてアメリカ合衆国へ渡った。アレクサンドル2世暗殺をきっかけにした混乱で、ウクライナ南部を中心に大規模なポグロムが起きた。その反動としてパレスチナに民族の拠点を設けようというシオニズムの運動も生まれた。最大のポグロムはロシア革命に始まる内戦期で、ウクライナを中心に白軍や民族主義者も加担して5万から20万人のユダヤ人が殺されたという。「ユダヤ人=農民の搾取者」に加え「=革命家」というステレオタイプも反ユダヤ感情を掻き立てた。
ここからナチのホロコーストまでは、ほんの一歩だろう。こう見てくるとホロコーストは歴史の流れのなかで突然出てきたものでなく、キリスト教圏に連綿と続く反ユダヤ感情の、ある意味現代的な現象であることが分かる。「現代的」というのは、伝統的な反ユダヤ感情に「人種衛生学」という科学的装いを与えたこと、さらに絶滅収容所という近代工場にも似た徹底性や機械的に冷たい装置を導入しことにある。
ところで、現在のイスラエル国家をつくる原動力となったシオニズムというのも、伝統的なユダヤ教とは異なったもののようだ。シオニズムは19世紀後半の東欧に生まれた。ユダヤ人は国を持たず放浪したり寄生したりする賤民と蔑まれないために、故地である「パレスチナに拠点を設け、農業を中心に自活することで、民族として自立する能力と意思を持つことを証明しようとした」のだ。とはいえ『モスカット一族』などを読むと、伝統的なユダヤ教の多数派からは、ユダヤ教の教義から外れて国家を建設しようとする若者のはねかえり、みたいな言い方をされている。19世紀は民族的ナショナリズムが高まり国民国家が形成された時代だから、シオニズムもそうした時代の流れのなかで生まれたものなのだろう。
もともと「ユダヤ人」とは、血縁的な集団であるとともに、ユダヤ教を信仰している者という、二つの側面を持つ。でも著者は、シオニズムの最大の特徴はユダヤ人を宗教集団でもなく過去のユダヤ人の生き方とも異なる、ネーションとして捉えた点にあるという。ユダヤ民族というネーションが形成するイスラエルという国家がどう振る舞うかについて、「シオニズムは最も徹底して非ユダヤ人の『ネーション』を模倣した」。模倣した対象は、例えば自分たちユダヤ人を迫害したナチスだろうか。とすれば、「迫害された者」が数十年を経ずしてパレスチナ人を「迫害する者」へと変貌したことの文化的背景も見えてくる。冒頭のニュースで見た、イスラエルに抗議するユダヤ教正統派の若者の映像は、そうしたユダヤ教とユダヤ人の変貌や流動化という流れのなかで考えるべきことなのだろう。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





